万年筆と吸取紙(すいとりがみ):その歴史と多様な使い方

吸取紙 は、万年筆やガラスペンを使う人々にとって、欠かせないアイテムの一つです。
その役割はインクの吸収にとどまらず、さまざまな用途で活躍します。
今回は、吸取紙の歴史からその基本的な使い方、そして現代における多様な利用方法についてご紹介します。
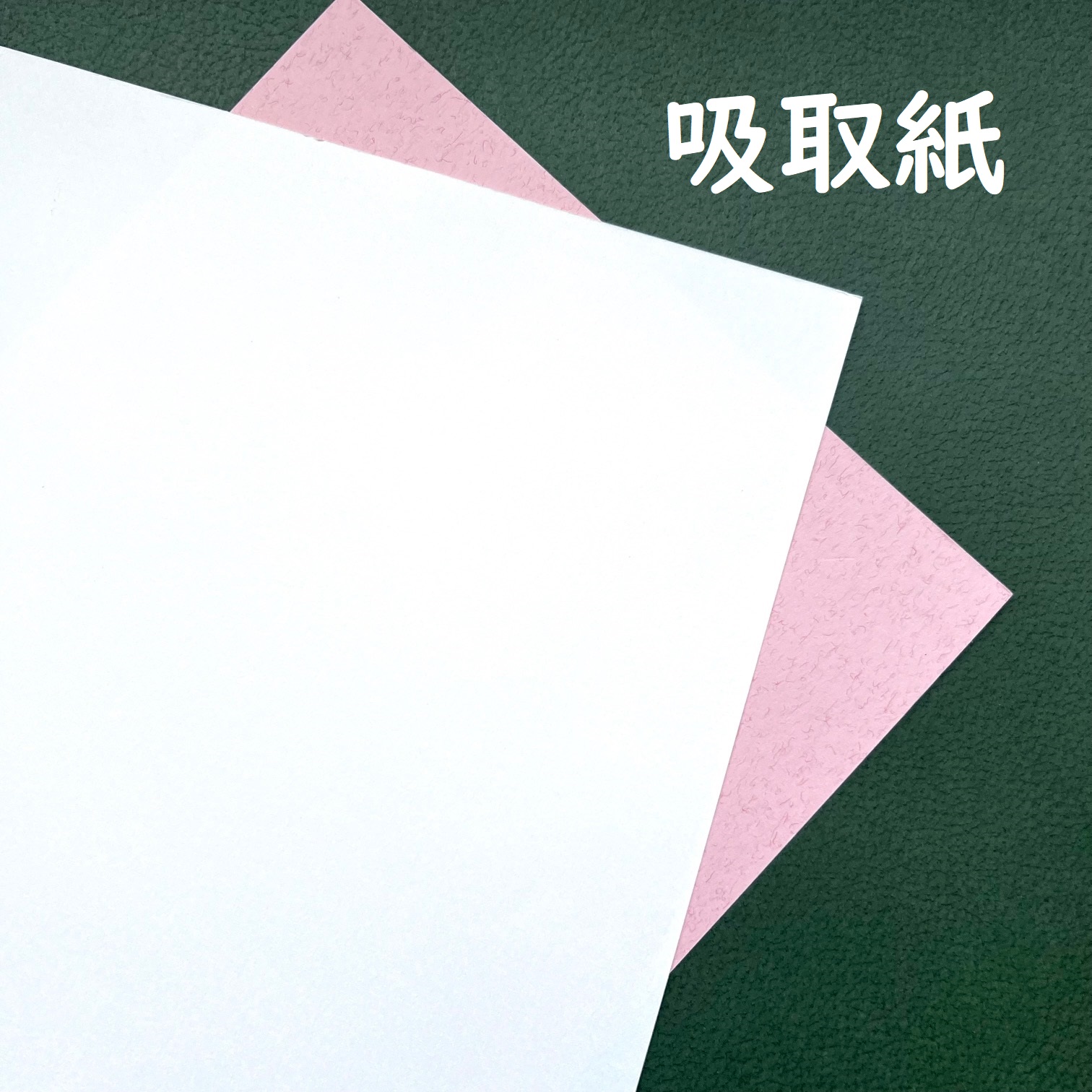
インクを使う作業のお供におすすめ。
万年筆やガラスペンなどのインクを吸い取り、乾燥を早めるための吸取紙です。
版画や水彩などの画材の用途やコースター・結露防止・芳香剤芯など水濡れしやすいところに置くことで水分を吸い取ってくれます。
吸取紙
| 全判寸法 | 色柄 | 連量 |
| 菊判T目 | 白、桃 |
69kg(#80) 0.21mm 90kg(#100) 0.25mm |
※断裁加工のお知らせ 通常A3、A4、B4、B5に断裁し販売しておりますが、菊判以下、1辺100以下のサイズであれば、ご指定のサイズに断裁が可能です。
別途料金550円をいただきますが、ご希望がありましたら断裁加工料金のページをご確認下さい。
吸取紙の歴史と起源
吸取紙の歴史は、書くための道具や技術の発展とともに進化してきました。
中世ヨーロッパではインクの乾燥を早める手段として砂などがつかわれていたようですが、吸取紙が広く普及したのは19世紀にかけてのことです。
その昔、イギリスで、インクが滲まない紙を作成している職人さんが、あるとき、滲まないようにするための薬剤を入れ忘れてしまったのだそうです。
できた紙は、不良品となり出荷できず、職人さんは困り果てていましたが、この紙が水をよく吸うことに気が付きます。
そこで不良品だった紙を、インクを吸い取るための道具として販売したところ大ヒット。
手軽に使える吸取紙は、またたく間に広まったといわれています。
この時代、万年筆やその他のペンが一般に普及し始め、インクの乾燥を早めるための手段が求められるようになりました。
吸取紙はその需要に応える形で生産され、オフィスや家庭で日常的に使われるようになりました。
しかし、20世紀に入り、タイプライターやボールペンが普及すると、吸取紙の使用は次第に減少。
それでも、万年筆や手書きの文化を大切にする人々の間では、今もなお吸取紙が愛用されています。

吸取紙の基本的な使い方と版画での応用
吸取紙は、万年筆やガラスペンのインクを吸収するために使用されるのが一般的ですが、版画の分野でも重要な役割を果たしています。
特に銅版画や水性木版画などの作業では、用紙を湿らせておくことがよくありますが、水分が多すぎるときに吸取紙が活躍します。
基本的な使い方としては、数枚の吸取紙を重ね、その上に滑らかな紙を置きます。
湿らせた用紙を吸取紙の間に挟み、バレンや手で圧力をかけることで、余分な水分を取り除きます。
また吸取紙は、インクや水分を吸い取るだけでなく、逆に湿した吸取紙に用紙を挟み、水分を与えるためにも使われます。
吸取紙のその他の用途と取り扱いのポイント
吸取紙の用途は、インクや水分の吸収に限らず、非常に多岐にわたります。
例えば、吸取紙は古い書類や本の保存にも役立ちます。
湿気や酸化を防ぐため、保存したい書類の間に吸取紙を挟んでおくことで、劣化を遅らせることができます。
さらに、版画や捺印・スタンプ作業、植物標本の作成、アートやクラフト、コップや窓の結露など、多くの場面で吸取紙が活用されています。
繰り返し使う場合は、湿ったまま放置すると吸水性が低下しカビの原因となることもあるので注意が必要です。
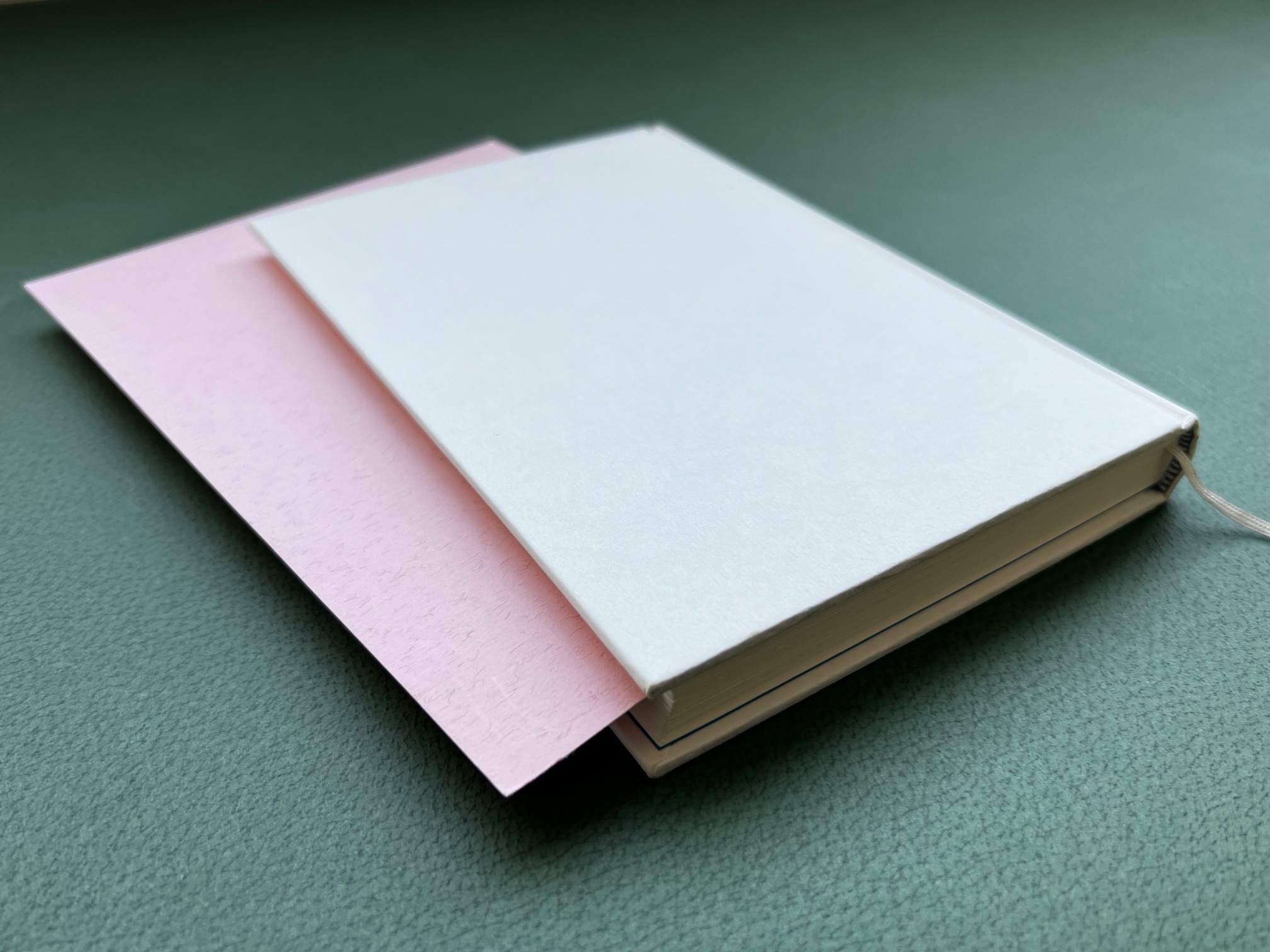
吸取紙は、そのシンプルさにもかかわらず、さまざまな分野で活躍する万能なアイテムです。
その歴史を知り、基本的な使い方や取り扱いのポイントを押さえることで、さらにその魅力を感じることができるのではないでしょうか。
吸取紙は、万年筆や版画の愛好者にとって、今もなお欠かせない存在であり続けています。
吸取紙をお持ちでない方も、ぜひ一度試してみてください。